君に会いたいと願い過ぎて、幻を見たのかと思った。それほどまでに俺は、昔の恋を引きずっていたのかと。
再会なんて望んでいないはずだった。遠くの町で、君が誰かと幸せにしているのなら、それでいいと思っていたのに…。
それなのにどうして俺たちは、もう一度出会ってしまったのだろう…。
今回は紫耀くんサイドからのお話です。
こちらはキンプリの曲「Doll」の歌詞からインスパイアされた小説です。
前のお話はこちら↓
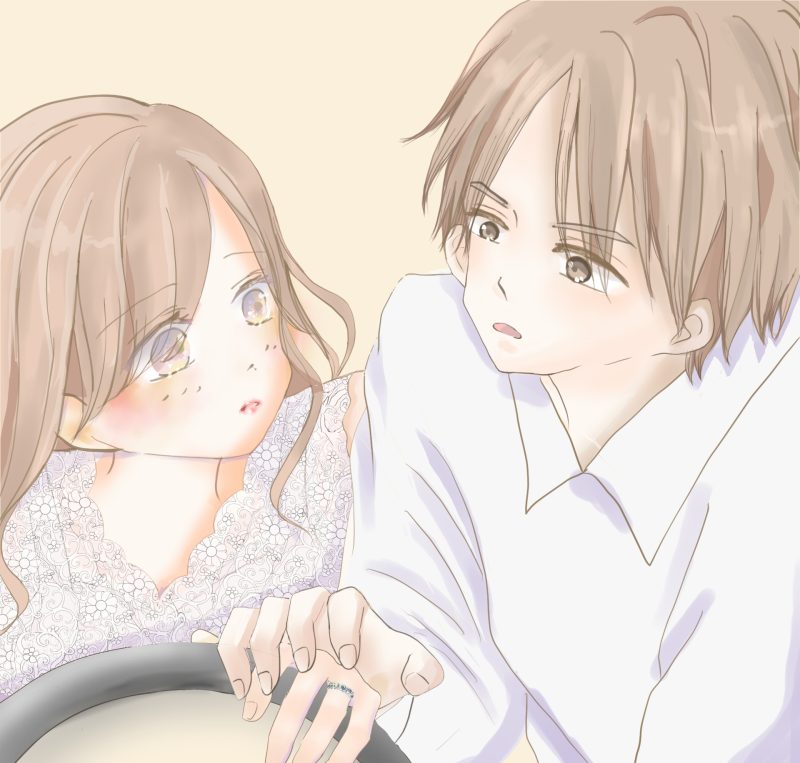
お祭りと再会(紫耀サイド)
その日は地元の小さな神社で祭りがあって、俺の恩人のおっちゃんが屋台を出すというので、俺も店番を手伝っていた。
「あ、りんごあめー!」
小さな子供が近寄ってきて、後からその子を追ってきた母親らしきその人を見たとき、息が止まりそうになった。
その人は、俺がずっとずっと忘れられずにいた初恋の人だった…。
毎年、7月7日は彼女のことを思い出す。
「これから毎年一緒に見ようね」と約束した。その約束を破ったのは俺のほうだけど…。
芸能界を辞めて東京を離れようと思ったときに、俺は逃げるようにあの町から離れた場所を選んだ。行く先はどこでもよくて、とにかく彼女の住んでいるあの町から離れたところならどこでもよかった。
偶然、彼女に会ってしまうことがないように。
この町を選んだ理由は、ただ、それだけ…。
地元の人間とは、高校時代の親友・ジンとしか連絡を取っていなかった。花凛が廉と結婚して、子供が生まれたことは、ジンから聞いた。
でも、花凛とジンもその後は疎遠になってしまったらしく、それ以上の情報は全然入ってこなかった。
だけど、突如、俺の前に現れた花凛の姿を見て、隣にちょこんとたたずむちょっと猫目のか細い小さな男の子が、廉にそっくりであることに気づいた。
「あ!ヨーヨーすくい!」
男の子が駆け出し、花凛がこちらをチラチラと気にしながらも追いかけていく。
「お~、店番さんきゅ~」
しばらくすると、おっちゃんが戻ってきた。
「おっちゃん!やばい!俺、ここから逃げなきゃ!」
「ん?なんかあった??」
おっちゃんとなんやかんややっているうちに、向こうから花凛が戻ってくるのが見えた。
「やばっ!おっちゃん!俺、いないから!よろしく!」
もう逃げる時間はなさそうなので、その場にしゃがみこんだ。
花凛「あれ?さっきここでりんご飴売ってた人は?」
何が何やら事情が分からずハテナ顔のおっちゃんがチラリとこちらに視線を落としたので、必死に口の前に指を立てて「シーッ!シーッ!」と頼み込む。
花凛「いたでしょ!?さっきここに、すっごいイケメンの!」
おっちゃんが冗談めかしてごまかしてくれ、花凛はうちの屋台から去っていった。
「なに?知り合い?」
「例の…彼女です」
「例の彼女って…例の!?」
おっちゃんが目をまんまるにする。
おっちゃんは、こっちに来てからいろいろと助けてくれた人で、俺も何でも話している。
花凛や廉には、最後まで本当のことは言わなかった。それが二人を守るってことだから。
でも、俺だって苦しかった。誰かに本当のことを聞いてほしかった。
どれだけ花凛のことを大切に思っていたか。本人にはどうしても伝えられなかった思いを、口に出して、誰かに聞いてほしかったのだ。
花凛のことが本当に好きだった。すごく大切だった。
だから…
あの町で、花凛は廉と生まれた子供と幸せに暮らしている。
それだけでよかった。
もう二度と会えなくても、彼女がどこかで笑ってくれているのなら、それだけでよかった。
あの家で、優太や海人に囲まれて、新しい家族となった廉と花凛と小さな子供が笑ってる。
そしてそこに…
俺はいない。
俺がいちゃいけないんだ。
そしたらみんな、笑えなくなるだろう?
…なんて、これじゃまるで俺が花凛や廉のためにかっこよく身を引いたみたいな美談になってしまうが、本当のところは、俺が花凛のそばにいたら、ずっと花凛を忘れられなくて辛いから。
だから逃げ出したんだ。
パーン…
花火が上がる。
小さな神社だから、少し向こうに男の子と手をつないだ花凛が空を見上げている後ろ姿が見えた。
8年ごしの約束、叶っちゃったみたいだ…。
俺たちは、少しはなれた場所から一緒の花火を見上げていた。
これじゃまるで、”運命の再会”みたいじゃないか。
パーン。
次々と打ち上げられる花火に夢中で、花凛はこちらには気づかない。
あぁ…確かあの日も、こんなふうに神社で花凛の後ろ姿を見つけたんだった。
あの時、声をかけていたら、俺たちの運命は違ったのだろうか…?
なんて…。今の花凛が幸せなら、運命を変える必要なんてないじゃないか。
もともといないことが正解の俺は、早く消えなきゃな。
「おっちゃん、もう手伝いいいっしょ?俺、帰るわ」
パーン。
まだまだ空を照らす花火に背中を向けて、俺は神社を出た。
”運命”を断ち切るように。
二度目の再会
アイドルを辞めて、まったく縁もゆかりもない片田舎に逃げてきた。
高校を辞めて芸能界入りした俺は、何の学歴も経験もなかったけど、ただ昔から車が好きという理由だけで、小さな自動車整備工場にふらりと立ち寄って、突然「あの~、雇ってもらえませんか?」と声をかけた。それがおっちゃんとの出会いだった。
突然芸能界から姿をくらました俺は、連日ワイドショーで「平野紫耀、突然の失踪…!!行方は…!?」などと取り沙汰されており、アイドルになんて興味のないであろうおっちゃんでもさすがに俺の顔を知っていた。
最初は驚いていたけど、訳ありなのだろうと察して深く事情を聞かずに雇ってくれた。従業員も少人数でみんないい人で、とくに詮索することもなく俺を受け入れてくれた。
それから時間をかけておっちゃんとの信頼関係は出来上がっていき、俺は今まで誰にも言えなかったすべての事情をおっちゃんには話した。
女という女に追い掛け回される人生だった。
車の工場での仕事はお客さんと触れ合うこともなく、黙々と機械いじりをしていればいいし、同僚はみんな中年の男くさい職場。追いかけ回されることや求められることに疲れていた俺には、ホッとできる最高の職場だった。
ただ一人だけ、自分から追いかけたい、すべてを捧げたいと思えた人は、俺に背中を向けて去っていったけれど…。
俺が東京に旅立った日、ホームまで追いかけてきてくれた君。本当はすべてを捨てて、君のことをこの手に抱きしめたかった。「振り向いて」と何度も心の中で叫んだけど、どうしても声に出すことはできずに、君は振り向かずに去っていった。
あの時、俺たちは終わったんだ。
だから、奇跡のような再会を果たしたけれど、これは運命なんかじゃない。そう自分に言い聞かせて、胸が切り裂かれるような思いで未練を断ち切って、花凛から身を隠して神社を去ったというのに。
あっさりと二度目の再会はやってきた。
おっちゃんの工場での暮らしは最高だったが、経営が悪化して工場はつぶれてしまった。おっちゃんは従業員たちにそれぞれ次の職場を世話してくれて、俺には付き合いのあった自動車学校の教官という仕事を紹介してくれた。がっつり人と触れ合う仕事なので少し戸惑いもあったが、何のツテもないこの町で一から職を探すのも大変だし、おっちゃんの好意を無駄にすることもできない。それに運転は昔から好きで、仕事自体に不満はないし、今まで自分がやってきたことと比べたらすごく健全だ。
そして、実際に仕事を始めてみると、教習生はみんな若い子ばかりで、俺のアイドル時代なんて知らない子ばかりだった。ちょっと自意識過剰だったな、と拍子抜けして、そしてそれだけ時は流れているのだと実感した。
その日、担当する教習生の待つ車に向かうと、いつもの若い子とはちょっと雰囲気の違う大人の女性が向こうに見えた。
「こんにちは~、担当の平野で…す」
振り返った彼女を見て、また幻でも見たのかと思った…。
車の中で、二人っきり!密室!!
やべぇ、緊張する…!!何話そう…!?
…って、教習中なんだから、運転の説明すればいいんだった。
緊張を打ち消そうと、ペラペラと運転についての説明を続ける。
花凛は真剣に俺の話を聞いてくれていて、じーっと俺の横顔を凝視してくるので、顎のあたりがムズ痒くなる。
いざ、エンジンをかけて車を発進させてみようとすると、花凛がテンパってハンドルをグリグリと左右に動かす。
「落ち着いて」
そういってハンドルを取ろうとして、花凛の手の上に俺の手が重なってしまった。
花凛が驚いたようにこちらを見上げ、至近距離で見つめあう。
付き合っていたころなら、こんな距離で見つめあえばこのまま自然とキスをした。
グロスが塗られてうるうるとした唇に、思わず息をのむ。
ノースリーブから伸びた二の腕は、昔より少しむっちりしていて、より俺の好みに近づいていた。
ゆるく巻いた髪も、総レースのブラウスから透ける白い肌も、高校生の頃よりも色気を増していて、他の男の教官に担当されたらどうしようと心配になるレベルだ。
俺だけのものにしたい…。
重なるその手を放すことができずに、そっとなぞるように久しぶりに触れたその手の感触を確かめる。
しかし、固くて冷たいものに指が当たって、俺はピタリを動きを止めた。
結婚指輪…。
次の瞬間、バッと手を振り払われた。
拒絶されたショックで一瞬頭が真っ白になったが、我に返って慌てて廉の話題を振る。
そうだよ、何考えてんだよ、俺!!
花凛は廉の奥さんなんだぞ!?子供もいんだぞ!?
密室の車内で教官が生徒の手を握るとか、セクハラ以外の何ものでもないじゃんか…!
「廉とはどう?家事とか手伝ってくれんの?料理とか」
「お兄ちゃんと海人と一緒に住んでるから、料理はほとんど海人まかせになっちゃって…」
「なんだよあいつ、約束守ってねーじゃん」
花凛は「なんのこと?」といった表情で首をかしげる。
昔から花凛は料理が苦手で、「もし花凛と結婚したら…」という妄想の世界の話で、俺と廉が言い争いになったことがあった。
俺は、嘘でも「おいしい」と言って料理を全部たいらげると言い、廉は「まずい」と指摘した上で自分も一緒に料理をすると言った。
俺は「全面的に守ること」が愛だと思っていて、廉は「一緒に成長すること」が愛だと主張していた。
俺はそんなふうにしか生きられなかったけど、あの時自分の弱さをさらけ出せていれば、どうなっていたのだろうと、今でも後悔に似た感情が浮かんでくることがある。
いろんなこと一切がっさい無視しちゃって、シンプルに「花凛が好きだ」という気持ちを伝えていたら、花凛は受け入れてくれたんじゃないかと。
その後も俺たちは、白々しくも花凛の結婚生活の話をした。優太や海人の名前が出るだけ、少しは緩和されるものの、花凛と廉が結婚したという事実、そして二人の間には子供がいるのだと、まぎれもないその事実を突きつけられ、俺は「へぇ」とか「そうなんだ」とか軽く相槌を打っているように見せて、そのたびに胸に一つずつ切り傷が増えていくみたいな痛みを感じた。
それでもそんな会話を続けた。そうすることによって、俺たちの再会には何の意味もないのだと、誰かに言い訳をするように。
その誰かは、廉に、花凛に、そして自分自身に。
視線
そして今度は俺のこの8年間の近況報告。
芸能界を辞めて人の目を避けて田舎に移り住んだこと、工場がつぶれて紹介された自動車学校で働くことになったこと、人と触れ合う仕事になったけど今の若い子は俺のアイドル時代を知らないから案外大丈夫なこと。
「俺ももう過去の人だからね」
「私はこの8年、忘れたことなんてなかったけど」
え…?
思わずその言葉の意味を考えて絶句する。
ーずっと忘れられなかった。ー
俺が花凛に抱いていたのと同じ思いを、花凛も抱いていたのかと、思わず勘違いしそうになった。
でも、「ずっと心配していた」って単純にそういう意味だよな。当たり前じゃんか。俺は突然姿を消して、一切連絡もしないで、そりゃあ家族は心配する。”廉の家族として”心配してくれていただけだ。
心の中で一人あたふたしている俺をさておき、花凛は何とはなしに話題を進めていく。
「若い子しか来ないと思ってたら、こんなおばちゃん来てびっくりした?」
「花凛、全然おばちゃんじゃないよ!もっときれいになっててびっくりした…!」
今度は花凛が絶句する。
うわ、俺、何言ってんだ…。花凛、困ってんじゃねーかよ!
「紫耀くん、昔から車好きだったから天職だね。誕生日プレゼントも車ほしいって言ってたもんね」
花凛は変な空気にならないようにと、話題をそらしたつもりかもしれないけど、付き合ってた頃の思い出話なんて、俺にとっては余計にあの頃の思いが蘇って変な感情が膨らむ。
「あぁ、言ったね、花凛とドライブするの夢だったから」
付き合ってた頃、たった一度だけ一緒に過ごした花凛の誕生日。
花凛は、次は俺の誕生日を一緒に過ごすつもりで、誕生日にほしいものを聞いてくれたけど、そんな未来は二人には訪れなかった。
「ほしいものは車」と答えた俺に、「それはさすがにあげられないけど」と花凛は笑った。
でも、別に俺は車そのものが欲しかったんじゃない。電車で出かけて買い物デートをしている間、ずっと周りの男たちから花凛に注がれる視線に気が立って、デートを楽しむどころじゃなかった。
だから車で二人きりでドライブデートができたら、花凛を俺以外の誰の視線にもさらすことなく独り占めできるのにって、そう思ったんだ。
だから、欲しいのは車じゃなくて、花凛だったんだよ。
だけどその願いは、俺の誕生日を待つまでもなく叶ったんだ。
二人きりでドライブで花凛を独り占めするよりも、もっと密閉した濃密な方法で、あの日、俺は花凛を手に入れた。
「じゃあ夢叶っちゃったね、ドライブ」
花凛がハンドルを握りながら、おどけたように言ってほほ笑みながら、少し首を傾けこちらに顔を寄せる。
その白くて細い首筋をたどり、Vネックの胸元へと視線を這わせる。シースルーのブラウスから透けるキャミソールは体のラインをむっちりとなぞっている。ノースリーブから伸びた二の腕は窓から差し込む光を受けて、弾力のありそうなハリ感を反射している。
あの頃何度も触れた花凛の柔らかさを思い出す。
あぁ、このままこの体に触れて、教習生に手を出したセクハラ教官としてクビになってもかまわない、そのまま逮捕されても別にいいか、と頭がくらくらしておかしな思考が膨らむが、ただ一つ、花凛に「久しぶりに会った弟の妻に手を出すなんてキモい、最低」と罵られることへの恐怖心だけが、やっとのことで俺の理性を保っていた。
キーンコーンカーンコーン。チャイムが鳴って、我に返り窓の外に視線をやると、何か突き刺さるような視線を感じた。
少し離れたところに車を停めた同僚の大坪真理子が、こちらに鋭い視線を向けていた。
慌てて車を降りて事務所に戻ろうとすると、後ろから花凛が追いかけてきた。
「紫耀くん…!」
真理子に聞かれたらヤバイと思った。
「ここではその呼び方やめよっか、他の人の目もあるから、平野先生、で」
とたんに花凛の表情が曇るのがわかった。すぐに言い訳をしたいけど、車を降りた真理子がこちらに向かって歩いてくる。
「はい…平野…先生」
花凛が寂しそうにポツリと呟く声を背中に受けながら、急いで花凛を距離をとった。
指輪が消えた理由
教習生の若い子はほとんど俺のことを知らないと言っても、同年代の同僚にはやはり昔の俺を知っている人がいて、転職してからすぐに猛アピールを受けた。
大坪真理子。今年で40になる。
愛想がなく厳しいため、若い子からの人気がなく、そのキャラクターと名字も相まって「お局先生」なんて教習生たちから呼ばれていた。
おっちゃんの工場も、工場の寮も、取り壊しが決まって、俺はしばらくおっちゃんの家に住まわせてもらっていたが、おっちゃんも借金を抱えて大変なことはわかっていたので、いつまでも甘えているわけにはいかなかった。
転職してすぐに引っ越しにかかるまとまったお金を工面するのは難しかったし、何より”女に甘えて生きていくこと”は、もはや俺の人生の中では当たり前になっていて、そこまで抵抗もなかった。
一緒に住めばこれ以上おっちゃんに迷惑をかけずにすむ。それどころか、家賃もいらない。食費も出さずに3食、飯が出てきて勝手に片付いていく。洗濯も掃除もやってもらえる。
こちらが支払う代償は、夜の相手をする。ただそれだけ。
おっちゃんのところで働かせてもらっている間は、俺はやっとまっとうに生きれている気がしていた。だけど、結局その生活も長くは続かなくて。やっぱり歯車が狂い始めると、また転がるように落ちていく。人生逆戻りだ。
もともと俺の人生は、花凛と別れたあの日から色を失っていたんだ。今さらがんばってちゃんと生きようとか、そんな情熱も気力もない。
楽な方へと落ちていくだけ。
年上の女は数えきれないほど相手をしてきた。今さらなんの抵抗もない。
「ねぇ、今日担当していた子って、もしかして知り合い?」
夕飯を作りながら、こちらを見ないで真理子が聞く。たわいもないことを話すような口ぶりだが、その背中に全神経が集中しているといったオーラが出てる。
「いや、別に?なんで?」
「そうなんだ。なんか親しそうに話しているように見えたから」
車の中で話しているのを外から見られただけなのに、やっぱり女のカンは恐ろしい。
翌日、朝からソワソワしていた。今日も花凛は来るだろうか?何時に来るのだろう?そればかりが気になって、事務所にいながらも受付の方ばかりチラチラを気にしていた。
そして花凛がやってきた。今日は、昨日よりももっとかわいく見える。
思わず見惚れていると、花凛がこちらに気づき、慌てて目をそらす。
どの時間のどの車に入るかは、こちらである程度調整できる。
花凛の取った予約票を見れば、自分が担当することはできるが、昨日の真理子の感じだと怪しまれるだろう。本当は今日も花凛と同じ車に乗りたくてたまらないが、今日はおとなしくしておいた方がいい。
焦らなくても、これから花凛はしばらくここに通うのだから、またいつでも会える。そう自分に言い聞かせた。
教習を終えた花凛が、廊下のベンチに一人座っているのが見えた。今日、初めて声をかけるチャンスだと思って近づくと、花凛は具合が悪そうだった。声をかけると、元気がない。体調が悪いだけではなく、精神的にも何か落ち込んでいるように見えた。
隣に腰を下ろし、あることに気づく。
え…?
花凛の左手の薬指に指輪がない。
昨日はしていたのに。え?なんで?廉と喧嘩でもした?
え?まさか、俺と再会した…から…とか……?
ない!ないよな!絶っ対ない!!ないない!
「紫耀くんって仕事何時まで?」
一瞬、仕事の後、ご飯でも誘われるのかと思った。
まさか、廉とうまくいってなくて、俺に相談したいことあるとか?もしかしてもしかして、廉と離婚考えててて、俺とヨリ戻したいとか…?それで指輪外してきたとか…⁇
俺から誘いたい。飯行きたい。二人っきりで話したい。
今日はちょうど早番で6時までだったので、余裕で行ける。でも、それを伝えてみたけど、花凛の言葉は続かなかった。
俺から誘いたい…。でも…子供いるし、夜出かけるのは無理だよな…。
膝の上に置いた手を下ろせば、すぐに花凛の手を触れられる。ずっと会えなかった時間が嘘みたいに、今、花凛は俺の隣にいる。すぐ近くに。
でも、その手には絶対触れちゃいけない。
「紫耀くん…」
花凛が何か言いたげな表情で俺を見つめる。
なんでそんな目で見るんだよ…。
甘えているような、すがっているようなその目に吸い込まれるように、喉元まで言葉が出かかかる。俺は花凛が俺を求めてくれるのなら、いつでも…
「平野先生!ちょっといいですか!」
パチンと風船が弾けるような感覚で、現実に引き戻される。真理子が事務所から顔を出して、鋭い声で俺を呼んだ。また二人で話しているところを見られるとまずい。急いでその場を立ち去った。
引き返せない
「やっぱりあの子、知り合いなんじゃないの?」
鍋を挟んで向き合いながら、真理子が今日こそは逃すまいという刑事のような視線を向ける。
今後も話したりはするだろうから、さすがに全く知らない人というのは通用しないか。
「あぁ~、実は高校の時のクラスメイトで」
「…やっぱり。なんで昨日は嘘ついたの?」
「いや、別に嘘ってほどでも…。俺も高校途中で辞めちゃってるし、1年も一緒にいなかったから、大した付き合いもなかったしさ。それで言わなかっただけだよ」
それでごまかせるほど、鈍い女じゃないのはわかってる。この後いろいろ問い詰められるのも面倒だし、何より、真理子のこのモヤモヤを何とかしなければ、矛先が花凛に向かう可能性がある。
それだけは避けたい。
真理子の気持ちを収める方法はわかってる。
鍋の電源レバーを「切」にすると、テーブルを少しずらして四つん這いのまま真理子に近づき、少し荒々しく唇を重ねる。
「えっ紫耀くん、どうしたの…急に」
戸惑ってるふりをしていても、本当は喜んでるのはわかってる。
そのままその場で押し倒し、馬乗りになる。
「ちょっと、こんなところで?ベッド行こうよ?それにまだ、ご飯の途中だよ?」
そんなこと言いながらも、ちょっといつもと違うシチュエーションに燃えることもわかってる。
「今、急にしたくなったから。待てない。いいでしょ?」
「もぉ~、しょうがないなぁ、…いいよ?」
こうしてあげれば、何も考えられなくなって俺の言いなりになることもわかってる。
これで真理子が花凛に対して敵意を見せることはないだろう。
別に花凛とどうなりたいというわけでもないし、俺は今後も楽な生活と微々たる金の節約のために、真理子との生活を続けていくのだろう。
もう引き返せない。
もう二度と、あの手に、あの肌に、触れることはできないのだから。
目をつぶり、強引に服をはぎ取り、真理子が「ちょっと待って…」とか「やっ…」とか(心にも思ってないだろうが)否定の言葉を口にするのも全く構わず、荒々しく抱いていく。
頭の中には花凛の姿が浮かんでいた。
こんな風に相手の気持ちなんて全く考えずに、自分の好きなようにできたらどんなにいいか。
俺はその夜、花凛にしたくてもできないことを真理子の体にぶつけて、頭の中で花凛を愛しまくった。
その頃、花凛が廉に愛されまくっていることも知らずに…。
5話はここまで!
今までのストーリーを紫耀くん視点で描いてみました。お互いの心の声が聞こえていたら、きっと結ばれていた2人。一体2人のすれ違いはいつまで続くのでしょうか。

6話へ続きます。



コメント